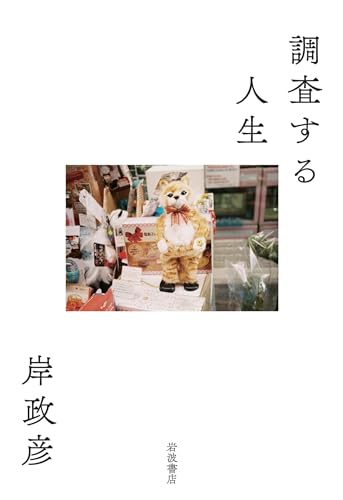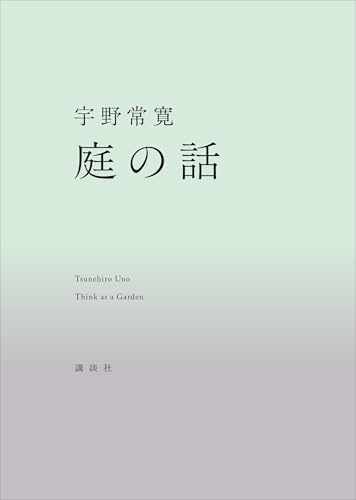今月読んだ本
今月(2025-08)読んだ本は4冊。
「俺ゲイやねん」と言った時に、「そんなこと関係ないよ、君は人として好きだから、人としてこれまで通り変わらない友達だよ」と良心的な人が言っちゃう。それは実はタブーで、それ言われるとせっかくカミングアウトしたのにそれを無にされた感じがして、傷ついてしまう、と……。
社会の本質はどっちかというと、つながってない、交換できない、ものすごい分断されてるところにあるんじゃないかと思って。
私はそもそも社会問題を解決したいという発想は薄いんですよね。
それよりはもうちょっと現実を知りたいとか、当時は女性のホームレスの人から、女性の先輩としての生き方を聞きたいという興味の方が先にありました。
人ってだいたい、私自身も含めて矛盾を抱えて生きているものじゃないですか。私はそういうのが見えた時に人間らしさを感じる。それが単に好きなんですよね。
貧困の問題は「することがない」ことの問題ともつながっている。単に所得が低い、失業が長いことだけで貧困は語れないように思います。スラムでは「すること」を求めてドラッグに手を出したり、インフォーマルなことをやったりする人が多い。
Sonewhere な人びとの大半は、ネジや歯車のような生に耐えるため、承認を求めてプラットフォーム上の相互評価のゲームをプレイする。そしてその低コストな承認の獲得のもつ中毒性で考える意志と力を失い、やがてゲームプレイを自己目的化するようになる。その結果として彼らはAnywhere な人びとに動員され、換金されていく。
そしてここで留意したいのがこのように Somewhere な人びとを中毒にして換金するプラットフォームの運営者たち=Anywhere な人びともまた、皮肉にも同じ構造の罠に陥っていることだ。なぜならばSomewhere な人びとのプレイする二十一世紀の<グレート・ゲーム>とは、Anywhere な人びとのプレイする金融資本主義という上位のゲームのデッドコピーにほかならないからだ。
そして、いま人びとはプラットフォームの要求する相互評価のゲームの速度に追いつくために、拙速なコミュニケーションを無反省に重ね、問題の内容ではなく他人の顔色だけを読み、考えることを放棄してより愚かになっていこうとしている。そして、インターネットが実現したはずの多様性をみずから放棄しようとしているのだ。
その結果として、人間は問題そのものに関与する動機を失い、そして世界のあるレベルから多様性は失われている。そこでここでは経済=場=プラットフォームから、そこで展開するゲームが与える快楽を相対化する方法を考えたい。それも家族とか、国家とか、そうしたつい最近まで、いや、こうしている今も多くの人びとを呪い、縛りつけているものに回帰することなく、プラットフォームの時代を内破することを考えたい。それが本書の主題だ。
人びとは自分の物語を求めて、ハッシュタグのついた実空間に動員されていった。もちろん、人間はそこで何ものにも出会うことはない。あらかじめ、ハッシュタグによって自覚された予定調和の事物にしか出会えない。街を歩いても、目当てのハッシュタグのついたもの以外目に入らなくなる。名所旧跡の前でセルフィーを撮る観光客が何ものにも出会えていないように。代わりに、彼らは相互評価のゲームに閉じこめられる。ハッシュタグとは、すでに多くの人びとが話題にしている事物を可視化する装置だ。彼らが触れているのは、事物ではなく人気のハッシュタグ=他のプレイヤーたちの発信の生んだタイムラインの潮流でしかないのだ。こうして実空間はサイバースペースに従属し、この閉じた相互評価のネットワークの内部に回収されたのだ。
私たちはまず、人間間のコミュニケーションは、放置すれば画一化するという事実を受け入れ、人為的な介入が必要であることを認めるべきなのだ。今日のインターネットは、人間間の承認の交換という雑藪に覆われ、それ以外の生物(コミュニケーション)が衰徴した、暗く、貧しい森なのだ。
他の誰かの自意識を感じさせる事物は、それを用いる人間の「手に馴染む」ことがなく、世界とのつながりを感じさせないからだ。前者をクリアしないためにエ業製品は、後者をクリアしないために美術品はそれぞれインティマシーを発揮することはない。
では、このとき二十一世紀のグレート・ゲームのプレイヤーー匿名で中傷を反復するプラットフォーム上のユーザーーたちは、『ビリー・バッド』の登場人物たちと比べたとき、「自由」な状態に近いのだろうか、それとも「強制」された状態に近いのだろうか。残念ながら、そして恐るべきことに圧倒的に「自由」に近づいている。それが私の結論だ。
前提として誤解されているがそもそも共同体とは圧倒的に強者が得をするシステムだ。比喩的に述べれば「この子が狐憑きだと肩じる」こと、つまり同じ物語を共有している集団が共同体だ。そこには主役がいて、重要な脇役とそうでない脇役がいて、端役がいて、そして悪役(数)がいる。その存在理由を説明できない、つまり物語をもたない共同体は持続できず、物語はメンバーの役割と立場を決定する。「敵」を設定することがこの役割の分担を明確にして共同体の結東をより強固にする。
要するに、ここでは共同体の与える不自由とブロックチェーン上のスコアの与える不自由がトレードオフになってしまっている。つまり共同体の内部での人間関係における「承認」をベースにした経済は人間を不自由にする。しかしそれを緩和するためにブロックチェーン技術を用いた社会的な「評価」を導入するとゲームの敗者が再挑戦できないディストピアが訪れるのだ。
誤解してはいけない。それは、「誰でも気軽に覗ける」「ゆるやかな」「標榜する価値はすぐに変わる」共同体「だから」こそ、おこなわれているのだ。彼らの目的は「家」の、「共同体」の維持であり、そこで語られる物語の内容や石を投げられる「敵」の存在は手段にすぎないのだ。
ここで重要なのは、個人が世界に関与しうるという「手触り」のようなものだ。ここで人びとに与えられるべき「手触り」は必ずしも輝かしくロマンチックなものである必要はない。したがってシリコンバレー的なものに憧れをつのらせる人びとが主張するように、いつの間にか「勤め人」が支配的になったこの国の産業社会を変えるために、彼ら/彼女らに対して意識高く「起業」をうながす必要などはまったくない。この例でいえばむしろ近年ようやく普及してきた副業や複業で「弱く」自立するモデルが、今日の日本においてはある程度有効だろう。
おそらく現代を生きる人類の大半が、好きなものを好きなように(所持金の許す範囲で)買う快楽よりも、情報発信によって不特定多数に認められる快楽のほうを重視している……というか、ふつうに「コスパがいい」ので優先的に追求しているはずだ。今日において、人間にとってもっとも簡単な自己表現は発信者になることだ。正確には、タイムライン上に無数に発生している共同性に接続し、敵を名指しして味方からの承認を獲得することがもっともコストパフォーマンスに優れた承認欲求を満たすための回路になる。