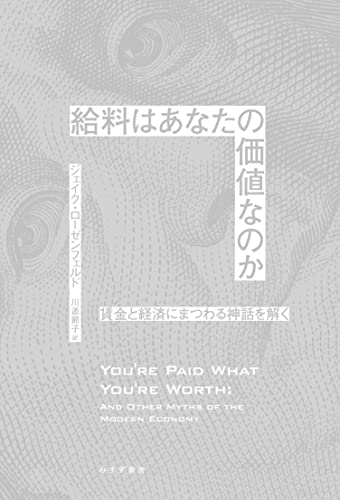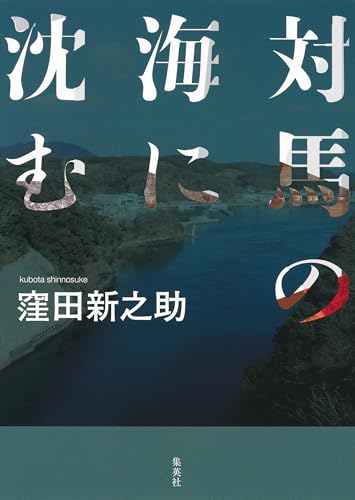今月読んだ本
今月(2025-10)読んだ本は3冊。
最低賃金の議論は、雇用に与える影響を中心にされることが多い。最低賃金を上げれば、雇用の伸びが抑制されるという理論である。しかし、実際には、雇用への悪影響はほとんど認められない。多くの場合、最低賃金の上昇は労働者の利益になり、雇用を減らさない、とデータが明らかにしている。国でいちばん高い最低賃金を採用したといえるエメリーヴィルには、ほかにも誇れる点がある。2・4%と低い失業率はアメリカ全体の失業率を大きく下回る。まわりと比べても低い。エメリーヴィルのあるアラメダ郡のほかの地域の失業率は、エメリーヴィルより17%高い。これは、最低賃金を上げれば失業率が下がるという話ではない。
エメリーヴィルに低い失業率をもたらした要因はたくさんあるだろう。だが、どのような仕事であれ、仕事を減らさずに給与を上げるのは可能だということだ。
洋服や家庭用品を販売する人たち、私たちが消費する動物を解体加工する人たち、私たちが出すごみを集める人たちにも支えられている。今現在、こうした業界では、権力は雇用主側に傾いていて、雇用主は労働者が使える資源がほとんどない状況を巧みに利用している。これらは確かに今は「悪い仕事」だが、良くなる可能性もある。場所や時代が違えば、良い仕事として存在している、あるいは存在していたのだから。
報酬労働法は、自社株買いの一部は認める一方で、従業員をないがしろにして株主に報いるこの行為の回数を制限するとしている。第5章で学んだように、企業には収益と投資家の利益を最大化する義務があるという考えは事実ではない。しかし、その影響力はあまりにも強く、今では多くのCEO、企業弁護士、ジャーナリストが真実だと思っている。従業員を含めたあらゆるステークホルダーに対して、取締役会が明確な説明責任を負うように法を改正すれば、この悪しき言念もなくせるかもしれない。
自社株買いは悪!
限界生産力を把握するのはきわめて難しいというノア・スミスの主張に対して、タイラー・コーエンは、個人の実績を測る手法が改善したために、それが原動力になって格差が広がっていると反論する。コーエンは「誰が何を生産したか測定できるようになるにつれて、たくさん生産する人とそうではない人の賃金の差は大きくなっている」と言う。
学界の一般的な流れとしては、成果主義による給与制度の導入には警鐘を鳴らす方向に向かっている。最近の研究からは、そうした制度を採用した企業では業務中に怪我をする率が高くなり、企業の業績も製品の品質も下がる傾向にあることがわかっている。
「報酬が測定実績に紐づけられると、必ず測定執着が改竄を招いてしまうのだ。」
測定の問題は、適切な基準をつくるにあたって選択肢が多すぎることではない。現代の仕事の多くでは、限界生産力を測ろうとしても、その試みはすべて誤った方向に向かってしまう。正しい方法が開発されていないからではなく、組織のなかである労働者と別の労働者の生産性を分けることはできないからだ。生産性は努力の集合体、社会的に成し遂げられるものとして理解されるべきであり、組織の目標を達成するために働く一人一人の仕事の総計として考えるべきではない。
今の技術は、荷物を積んで降ろすまでの時間を自動的に算出するし、何か規則に違反したときには記録する。つまり、雇用主は運転手の正確な生産性を測ることができる。そして、それが数十年前に劣らないことがわかっている。それどころか、1970年代末の運転手に比べて生産性が2倍になっているとする測定結果もある。生産性については十分だろう。
低賃金はウォルマートのDNAに刻みこまれている。
中略
現在、ウォルマートは約150万人のアメリカ人を直接雇用している。2019年には約157万人だった。つまり、アメリカの雇用の100件に1件はウォルマートという計算になる。連邦政府をのぞいてそんな雇用主はない。
株主資本主義とは、収益が労働者ではなく、経営者と株主に分配されるようになったシステムである。これが、ここ数十年のアメリカ人労働者の賃金の停滞につながっている。労働者の賃金は、さまざまな形で影響を受けている。もっとも大きいのは、給与そのものの削減である。株主資本主義が広まるにつれて、給与が株価と連動するようになった経営者は、手っ取り早く利益をあげる戦略に走った。売上を伸ばすという、時間がかかって不確実な道を行くのではなく、最終損益を改善するという近道を取ったのである。コストを削減し、資産効率を求める投資家の気をひくために、人員削減を選択した・その効果はすぐに出る。もちろん、労働者にとっては痛みもやってくる。合併や買収の増加は人員整理に拍車をかけ、新しくできた企業の余剰人員は出ていくドアを示される。合併を防ぐために人員整理が行なわれることもめずらしくないという。
ロイターの記者ティモシー・アペルは、2017年に中西部の小さな工業都市を訪ねた際、人々がこれ以上工場の仕事を必要としていないことに驚いた。「この町の人々にとっての問題は、量ではなく質である」
西山はルフィに熱烈ともいえるほどの憧れを抱いていたのではないか。彼が自分を慕う同僚たちに利益を与えてきたのは、「麦わらの一味」のような仲間づくりをしようとしたためではなかったのか、と。